歯が揺れを自覚してから歯周病ではないかと来院される方が多くいらっしゃいます。
歯周病の初期は自覚症状に乏しく、歯が揺れ始めるのは、歯を支えている骨を半分近く失ってからなのです。
失った骨を取り戻すことは難しく、多くの時間と苦労が伴います。
歯が揺れる前に、少しでも気になることがあったら相談してほしいですね。
骨を失ってしまった場合は、骨を取り戻すことを目標にするか、これ以上、骨を失わないことを目標にするかを決めていただき治療に臨みます。
歯を残すためには、一緒に頑張るしか方法はないのです。
治療に近道はありません。

歯周病とは
About Periodontal Disease
歯周病は口腔内で最も一般的な疾患であり、成人の約80%がその影響を受けています。
歯周病は進行すると歯肉の炎症や歯を支える骨の破壊を引き起こし、最終的に歯を失う原因となります。加齢と共に唾液の減少により、歯周病菌の繁殖が促進されることが特徴です。
また、歯周病菌が放出する毒素や炎症物質は血流を通じて全身に影響を及ぼし、動脈硬化、脳梗塞、心筋梗塞などのリスクを増加させることがあります。
さらに、糖尿病の進行を加速させる可能性も指摘されています。
定期的な歯科検診と適切な治療、そして効果的な予防策が重要であり、早期の対応が歯と全身の健康を守るために不可欠です。

歯周病の原因
原因1:プラーク(歯垢)
歯周病の主な原因はプラーク(歯垢)です。プラークは細菌が繁殖した粘着性の物質で、適切な歯磨きが不足すると歯の表面に付着します。放置すると硬化して歯石となり、日常の歯磨きでは除去できません。歯周病菌は歯周ポケット内で毒素を放出し、歯肉や歯を支える組織を破壊します。定期的な歯科検診で歯石を除去し、早期予防と治療を心がけましょう。

原因2: リスクファクター(危険因子)
歯周病のリスクファクターには、喫煙、不適切な食生活、ストレス、糖尿病などの生活習慣や、唾液分泌量の低下、歯並びの乱れといった口腔内環境の要因が挙げられます。これらの危険因子は歯周病を悪化させるだけでなく、治療の効果を妨げることもあります。歯周病が生活習慣病の一種とされるのは、こうした要因が深く関与しているからです。

歯周病を進行される因子
- 糖尿病
- 不適合な補綴物や入れ歯
- 継続した喫煙
- 不規則な食生活、ストレス、全身疾患(骨粗鬆症、ホルモン異常)
- 歯ぎしり
- 長期の薬の服用、免疫抑制剤を飲んでいる(免疫低下の状態)
- くいしばり
- 適切な歯磨きの不足
- 噛みしめ
- 口呼吸の方
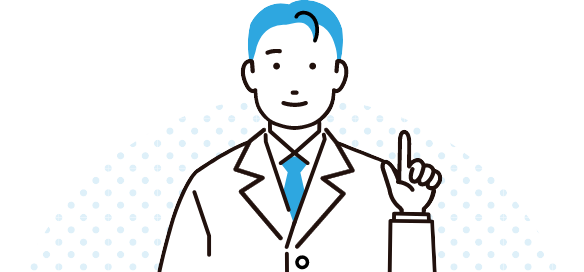
心当たりがある方は歯周病になりやすく、進行が速い傾向があります。
歯周病予防には、適切な歯磨きとリスクファクターを少なくする事が大切ですが、歯科での定期的な予防治療が効果的です。

歯周病の進行と症状
Progression of Periodontal Disease
01歯肉炎
歯に残った食べカスを栄養源として細菌が増殖し、粘着性のある細菌の集合体(プラーク)を形成します。これが原因で歯ぐきに炎症が起こり、腫れが生じることで、歯と歯ぐきの間には2〜3mmほどのすき間ができてしまいます。
自覚症状
- 歯磨きや固いものを食べる際、歯ぐきから出血する
- 歯ぐきが腫れる

02歯周炎(軽度)
歯周病菌は歯ぐきだけでなく、歯の周囲にある組織にも侵入し、やがて歯を支えている骨(歯槽骨)を徐々に壊し始めます。歯ぐきの腫れや赤みはさらに強くなり、歯みがきの際に出血することもあります。炎症が進行すると、歯と歯ぐきの間の溝は3~5mmほどの深さとなり、「歯周ポケット」と呼ばれる状態になります。この歯周ポケットは歯ブラシが届きにくく、内部には歯垢や歯石が少しずつ蓄積されていきます。
自覚症状
- 歯ぐきがぷよぷよする
- 歯ぐきに赤褐色や濃赤色の箇所がある
- 口臭がある

03歯周炎(中等度)
炎症がさらに進行すると、歯周ポケットは一層深くなっていきます。歯を支える歯槽骨の破壊も進み、骨の約半分が歯周病菌によって溶かされることで、歯がグラグラと動き出します。歯ぐきは後退し、歯が以前より長く見えるようになり、出血に加えて膿が出ることもあります。
自覚症状
- 歯ぐきを押すと血や膿がでる
- 強い口臭がある
- 起床時、口中がネバネバする

04歯周炎(重度)
歯ぐきが大きく後退し、歯の根元が露出してきます。歯槽骨の大部分が溶けてしまうため、歯がグラグラするだけでなく、やがて自然に抜けてしまうこともあります。この段階に至ると、歯を残すのが難しくなり、多くの場合で抜歯が必要となります。
自覚症状
- 歯を指で押すだけで、今にも抜けてしまいそうになる


歯周病による全身疾患
Systemic disease by Periodontal
歯周病の悪影響は、口腔内だけに限られません。
歯周病は細菌による感染症であり、増殖した歯周病菌が血流に入り込むことで、全身をめぐり、口とは無関係に思える臓器にも悪影響を及ぼすことがあります。
糖尿病
糖尿病と歯周病の間には、深い相関関係があります。実際に、糖尿病は歯周病の合併症のひとつとされています。歯周病は、血糖値を下げる働きをもつインスリンの分泌を妨げるため、血糖値が上がりやすくなり、糖尿病の症状をさらに悪化させる原因となります。歯周病自体が糖尿病を引き起こすわけではありませんが、糖尿病をお持ちの方には、歯周病の予防・管理にもぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。
狭心症・心筋梗塞
歯周病が引き起こす全身疾患の中でも、特に深刻な影響を及ぼす可能性が高いのが心臓病です。
心臓手術を受けた後、手術部位に歯周病菌が付着することで、症状が悪化することがあるとされています。また、心臓手術後は血液をサラサラにする薬を服用することが多く、その期間中は出血リスクが高いため、歯石除去や進行した歯周病の治療として抜歯を行うことができません。したがって、心臓手術を受ける前には、歯周病の治療をしっかりと終わらせておくことが重要です。
脳梗塞
脳梗塞も、歯周病が原因で引き起こされる可能性のある疾患の一つです。
歯周病菌が血流に入り込み、動脈硬化を引き起こすことで、脳梗塞を発症するリスクが高まります。
早産・低体重
妊娠中の女性にとって、歯周病の治療は非常に重要です。
歯周病菌が羊水に入り、毒素を放出することで子宮が刺激され、早産や低体重児が生まれるリスクが高まるというデータがあります。
誤嚥性肺炎
誤嚥性肺炎は、特に免疫力が低下している人や高齢者に多く見られる病気です。
お口の中で増えた細菌が唾液と一緒に飲み込まれ、通常は食道に流れるべき唾液が誤って肺に入ってしまう(誤嚥)ことで、肺が細菌に感染し発症します。免疫力が低下しているときこそ、お口の中を清潔に保つことが非常に重要です。
その他の疾患
歯周病の細菌は、肺機能の低下や肺炎、関節リウマチ、腎炎などの全身疾患を引き起こす可能性があります。歯周病の細菌は口腔内だけでなく、全身にもさまざまな悪影響を与えるのです。
そのため、定期的な歯周病治療や口腔内のメンテナンス、日々のホームケアをしっかり行い、お口の中を清潔に保つことが、全身の健康リスクを減らすことにつながります。

歯周病治療の流れ
Treatment flow
1
歯周病の検査
歯周病の検査では、歯周ポケットの深さや歯と歯茎の接触状態を評価する歯周ポケット検査、歯の揺れを測定する揺れの検査、歯周組織や骨の状態を確認するレントゲン検査、そして口腔内の状態を視覚的に把握する口腔内写真撮影を行います。これにより、炎症や組織の退化の程度を評価し、適切な治療計画を立てることが可能です。
2
清掃状況の確認と改善
歯周病予防には、日々のブラッシングが重要です。現在の清掃状況をチェックし、正しい磨き方を指導することで、磨き残しを減らします。歯周病の主な原因であるプラーク(歯垢)が取り除けないと、治療の成功や進行防止は困難です。単なるクリーニングだけでは予防効果が低いとの報告もあるため、セルフケアの改善が必要不可欠です。
3
歯石除去
歯石除去では、歯の表面に付着した歯石と歯茎内部の歯石を徹底的に取り除きます。歯茎の中の歯石除去は痛みを伴う場合があるため、必要に応じて麻酔を行います。この工程により歯周病の進行を抑え、健康な歯茎を取り戻すことが可能です。軽度の歯周病であれば、このステップのみで治療が完了するケースもあります。
4
歯周外科手術
重度の歯周病では、歯周外科手術が必要になる場合があります。この手術では、歯茎を切開して歯周ポケットを清掃し、骨や歯周組織を再生または整形します。しかし、術後の清掃が不十分だと歯周病が再発・悪化する可能性が高いため、適切なブラッシングや定期的な専門ケアが不可欠です。手術とセルフケアを組み合わせることで、治療効果を維持します。
5
メンテナンス
歯周病は再発しやすいため、治療後のメンテナンスが不可欠です。定期的なメンテナンスでは、歯周病の再発を防ぐための清掃や検査を行い、健康な口腔環境を維持します。通院の頻度や内容は患者さまの状態に応じて決定し、詳しくご説明いたしますのでご安心ください。継続的なケアにより、歯周病の再発リスクを低減し、長期的な健康をサポートします。

 院長から歯周病についてのメッセージ
院長から歯周病についてのメッセージ